『どうして?どうして僕なの…?』
散々犯され、泣きわめき叫び絶望する日々。
そんな中で涙ながらにこう尋ねたことがあった。
この問いかけに彼は何と答えたのだったか。
『欲しいんだ、どうしても。継ぐ者が欲しい。片方だけでは…駄目だったんだよ』
よく分からなかった。
今も、よく分からない。
ただ、彼は毎日ボロボロだった。
必死だった。
まるで何かに取り憑かれたように毎日僕のところに来ては、まだ駄目だと言って歯噛みする。
『まだ駄目』の意味は分かる。
それが『やっと叶った』になったとき、自分に何が起きるのかも分かっていた。
だから、早く逃げなきゃって、出口の無い部屋でいつも思っていた。

7
「で、何で浴衣?」
レッドは明らかに険のこもった目つきでグリーンを見た。
「いやぁ、貸してもらえてよかったな!俺の顔の広さが分かるよなぁ~」
「だから、何で浴衣…?」
「や、俺甚平じゃん?おそろいって感じでいいじゃん」
「じゃあ僕も甚平でいいじゃん」
「女物は余ってなかったんだよ」
「じゃあ男物でよかった」
「まぁまぁそんなこと言わずに。ばれたくねーんだろ?」
ニヤニヤとこちらを見てくるグリーンを本気で殴りたい気持ちにおそわれる。
それをグッと堪えてレッドは前で文庫結びにした帯を後ろに回した。
赤地に金色の金魚が踊る上品且つ華やかな浴衣は、どこから借りてきたのかは分からないが後夜祭のために準備されたものらしい。
対してグリーンはタコ焼き屋をやっていた際に着ていた、紺に黒の縦縞が入った甚平のままである。
クラス全員甚平を着ていたようだから、予備がないというのは些か不自然である。
まさか…とグリーンのほうを再びじと目で見るが、グリーンはどこ吹く風でポケモン何にしようかなぁと楽しそうに呟いている。
レッドは釈然としないままウィッグをかぶり、二つに分けた髪を片方ダッカールで留めると、口に咥えていたゴムで器用におだんごを作ってピンで留めていった。
所要時間3分ちょっと。
最後に赤い大輪の牡丹をおだんごの横に留めたところで、グリーンがぽかんとしてこちらを見ているのに気づいた。
「な、何…?」
「レッド手際良すぎじゃね…?」
「…っ」
しまったと慌てて目をそらす。
髪はいつもやってるから、浴衣は店で着たことがあるから、などとは言えるはずがない。
余談だが着物の着付けも自分で出来たりする。
「えっと、昔こういうの手伝わされたことがあって…それで覚えたっていうか…」
「へぇ…」
我ながら苦しいと思うが、それくらいしか咄嗟に思いつかなかったレッドは恐る恐るグリーンを覗った。
が、そこには「すげぇ」と顔を輝かせるグリーンが。
実際、自分のをやるのと人にやるのとでは全然違うので、レッドが鏡も見ずにここまで出来るのは今の理由では成り立たない。
しかしそんなことにとんと縁のないグリーンには十分な理由だったらしい。
「しかしまぁ…似てるよなぁ…」
「…誰に?」
「前にも聞いたじゃん。"紅"っていう子にレッドがすんげぇ似てるんだって。並んだら双子並だぜ絶対」
まじまじと見つめられてレッドは耐えきれずに再び目をそらせた。
絶対親戚…いや姉弟か双子だろとしつこく詰め寄ってくるグリーンの足を思い切り踏みつける。
本日二度目の足への襲撃に、グリーンは悲鳴を上げてレッドへ非難の目を向けてくるが、口をへの字にするレッドにこれ以上問い詰めても無駄だと判断したのか、溜息をついてそばにあったベンチへと腰を下ろした。
影で作業していたレッドも、足履きまで一通り身支度が整うと荷物を挟んでグリーンの隣に座った。
端から見れば美男美女の和服カップルだが、生憎何の催し物もない裏庭には人はほとんどいないためはやし立てる人もいない。
「っていうか、仮装しなきゃバトル参加出来ないって何なの?」
「あぁー…あれだろ、一イベントとして盛り上げたいんだろ」
要するに普段出来ないことを…ということらしい。
前のようにジャージで出ようとしていたレッドにはとても嬉しくないオプションである。
さすがに浴衣に帽子をかぶるわけにはいかないので今回は顔出しということになる。
そのことに不安を感じるものの、エントリーはもう済ませてしまっているため後戻りはできない。というかしたくない。
「…手ぇ抜いたりしたら許さないからね」
「こっちの台詞だよ」
こっちは金券までかかってるんだからな!と偉そうに言うグリーンに思わず口元が緩みそうになるのを耐えて、レッドはグリーンに懐から出したメモ用紙を押しつけた。
不思議そうな顔をするグリーンに、「使用ポケモンとそのポケモンが覚えてる技」と付け足す。
「って、もう選んできたのか!?」
「うん、先に欲しいの捕られちゃったら嫌だし」
先に、と言ってもレンタルポケモンの品揃えはかなり豊富である。
別に先に選んでも後に選んでも変わらない気がする…と思ったグリーンだったが、メモされているポケモンの名前を見て目を見開いた。
リザードン、カメックス、フシギバナ、カビゴン…
「これ、前の時といっしょ…?」
「うん、同じ子選んできた」
「同じ子って…」とグリーンは呆れた顔でレッドを見る。
「そんなんボールの外から見て分かるのかよ」
「分かるよ。ポケモンはみんな違う顔してるからね」
グリーンは今度こそ完全に絶句した。
自分のポケモンと他のポケモンの顔なら何となく違いは分かったものだが、レンタルポケモンの顔まで覚えているなんて…
「せっかくあの子たちのことちょっとだけ分かったから、もっと知りたいなぁって」
「…ん?あとはラプラスとエーフィ……。ピカチュウ使わねぇの?」
前回はそのピカチュウにボロ負けしたグリーンである。
しかしレッドは首をゆるゆると横に振った。
「違うピカチュウなんて使ったら僕のピカチュウが拗ねちゃうから」
腰のあたりのボールがカタカタ小さく動くのを感じて、レッドは内心でごめんねと手を合わせた。
本当は使ってあげたい。
思い切りバトルさせてあげたい。
しかしその最強の相棒は今回ばかりは使ってあげられない。
さすがに外部から人が来るとなれば、ピカチュウだけレベルが明らかに高いことが分かる人が出てくるだろう。
「っていうかダブルバトルになるってこと忘れるなよ…?」
「グリーンが僕に合わせてね。そういうの得意そうじゃん」
「おまえなぁ…!」
それなら一緒にポケモン選ぶぞ!
そう言ってグリーンは立ち上がると会場の方にずんずん歩いて行く。
その後を小走りに追いかけるレッドの目は少しだけ楽しそうだった。
***
タッグバトル。改造されたバトルフロア。そして強制仮装。
これだけの餌があれば観客が飛びつくのも当然で…
「うるせぇえぇえええっっ!!何も聞こえねぇよ!!」
「グリーンもうるさいよ」
「うっせぇ!!」
要するに、会場の観客席は人で埋まっていた。
本気で観客席に隙間が見えない。さすが文化祭。
グリーンは観客の歓声に耳をふさぎつつ、先ほどからポケモンをボールから出して何かしているレッドに近づいた。
ポケモンは会場に入ってからしか出してはいけないことは徹底されている。
レッドは会場に入ってから時間がないとばかりにポケモンを全員外に出していた。
エーフィを除く5匹が巨体のため、端から見れば怪獣に女の子が飲まれようとしているような光景である。
「みんな元気だった?久しぶりだね。また一緒に戦ってね」
よしよしと撫でてやれば巨体軍団が嬉しそうに鳴き声をあげる。
グオォオォオ、とか、ゴォオォオオとか。
グリーンは思わずレッドに近づく足を止めていた。
怖い、怖すぎる。
というか、何故レンタルポケモンがトレーナーにあんなに懐いてるんだ。おかしいだろ。
グリーンの心の叫びなど聞こえるはずもないレッドは一匹ずつに何事かを話しかけてはギュッと抱きしめていく。
そして最後に大人しく座っているエーフィに近づいた。
「エーフィは初めましてだね。よろしく」
レッドはエーフィのその美しい紫色の目をジッと見つめる。
エーフィもレッドを品定めするかのように、その深紅の目をジッと見つめる。
見つめ合うこと十数秒、エーフィはゆっくりと立ち上がるとレッドに向かって恭しくお辞儀をした。
「!?」
グリーンが唖然とするそばで、レッドは嬉しそうにエーフィの前にしゃがみ込み、その紫色の上品な毛並みを撫でた。
エーフィにも何事かを話している。
さすがに内容までは聞き取れなかったが。
グリーンが固まっているうちに、レッドは満足したのか全員をボールに収めてグリーンのほうに歩いてきた。
そこでやっとグリーンはハッと我に返る。
「お、おおおまえいったい何やって…」
「…?ミーティングだよ」
首をかしげてそう答えるレッドは、仕草は可愛らしいものの、その目は完全に闘志でぎらついていた。
そして始まった第一試合。
結果から言えば、一応勝利はしたものの中身はボロボロだった。
「ねーよ!!無理!!おまえのポケモンが技出すタイミング分かんねーもん!!」
「ポケモン見てれば分かるでしょ」
「分かんねーよ!っていうか4匹も目がいかないし!」
レッドは呆れたような顔でこちらを見てくる。
グリーンはグッと歯噛みすると、次の瞬間「あ"ー!」と叫んで頭をガリガリかいた。
レッドは前回と同様、ポケモンに技の指示を出していなかった。
だから、なんというか、要するに、タイミングどころか何の技を出すのかもグリーンには分からない。
「おまえどうやって指示出してんの?さっぱり分かんねーんだけど」
これは前回のバトル後も聞きたかった質問である。
隣で見せつけられて、改めて隣に立つ浴衣の少年の凄さを知った。
「指示…ね。僕は技を出すタイミングを合図するだけ。技の指示はしてないよ」
「はぁ!?」
「何を出せば良いのかはポケモン自身が一番分かってる。迷ったときはこっちを見てくるから、指で1から4を示してあげるだけ。さすがにアイコンタクトじゃつきあいの短いポケモンだと分からないから」
いや、それでも十分化け物級だという言葉をグリーンはグッと飲み込んで、その1から4の順番はどう決めているか問う。
あいうえお順かと想像していたグリーンだったが、レッドから返ってきたのは「得意な技順」という答えだった。
「だからどーやって!?」
「だから直接聞いただけだよ」
レッドはグリーンの剣幕に押されつつぼそぼそと答える。
グリーンは今度こそ頭を抱えてしまった。
レンタルポケモンとどうしてそこまで意思疎通出来るのかが分からない。
「ホントは声で指示してあげたいけどね。女の格好で男の声はまずいでしょ…」
レッドは恨めしそうに襟元の集音マイクを指さした。
前回もそうだったが、ここのバトルではトレーナーの声が観客席にも聞こえるようにマイクの装着が義務づけられている。
下手に喋れば会場全体に自分の声が響き渡ることになるのである。
「裏声で頑張れよ。レッドそこまで声低くないからいけるって」
「…無茶言わないでよ」
静かに睨み付けられ、グリーンも黙って口を閉じる。
レッドはグリーンに先ほど渡したメモの技名に、それぞれ1,2,3,4を書き込んで、それをぶっきらぼうにグリーンの胸へと押しつけた。
「…分からないなら覚えて。それくらい楽勝でしょ?指の合図は次から毎回やるから」
「…文武両道の俺様をなめんなよ?」
グリーンはもらった紙を十数秒ながめるとそれをくしゃりと丸めた。
「でも、僕のほうばっかりじゃなくてちゃんとポケモンを見ててね。ジッと見てれば、だんだん分かってくるよ」
「…じゃあ、俺も次同じポケモン使ってみようかな」
「…?」
「レッドが前回の数回の試合で今のポケモンとの関係を築いたなら、俺もちょっと真似してみたいって思った。それだけ」
そう言うと、レッドは別にいいんじゃない?と小さく笑った。
その顔が可愛すぎて動悸がしたことは絶対にレッドには内緒である。
そして二試合目は、運が良いのか悪いのか、ヒビキとコトネが対戦相手となった。
「ヒッ、ヒビキくん見てぇぇえぇええええっ!!グリーンさんの隣にいる人!!前回の定期バトルの優勝者!!!!」
「え?そうなの?」
ヒビキが目を凝らしてグリーンの隣に立つ女子を見る。
ヒビキもコトネと同様前回戦ってボロ負けしたのだが、前回はジャージでしかも帽子をかぶっていたため、顔がよく分からなかった。
遠目で分かったコトネに感心しつつ、同時に再びあの時の焦りが蘇る。
「コトネ、分かってるよね…?バトルにちゃんと集中し…」
「はぁあぁぁあああっ、すっごい綺麗…/////グリーン先輩知り合いだったんだ…!っていうか和服お揃い!?まさか彼女!?羨ましい…!あとで紹介してもらおっ!!」
今にもぴょんぴょん飛び跳ねそうな勢いのコトネを、ヒビキは呆然と見ていた。
これは駄目だ。いろんな意味で駄目だ。
冷や汗が背中を伝っていく。
「コ、コトネ!」
ヒビキはコトネの肩をガッと掴むと、無理矢理自分の方へ向かせた。
いきなりのことにコトネはきょとんとしてヒビキの方を見る。
「こ、これはタッグバトルでっ、二人が協力しなきゃ駄目で…!だからコトネは、ちゃんと僕のほうを見てて!!」
「ヒビキくん…」
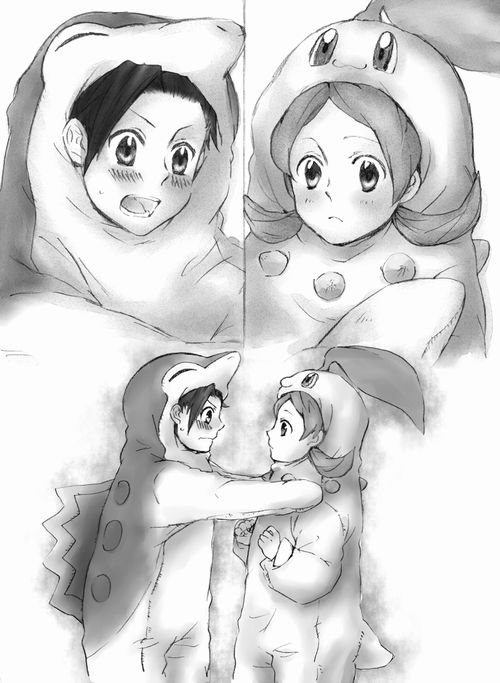
コトネはしばらく赤く染まったヒビキの顔を見ていたが、不意ににっこり笑った。
「当然だよ!絶対勝とうね!二人ともフルボッコにしちゃおう!ほら、やっぱり、残念だったねって言って不敵に微笑んでくるのもいいんだけど、負かせて打ちひしがれた表情はもっと見たいっていうか、打ちのめされるのもいいんだけど、それ以上にあの人を打ちのめしたいっていうかーーーー!!!!!」
頬を上気させて捲し立てるコトネに、ヒビキは目の前が真っ暗になった。
***
白熱したバトルの末、結果は4対2でレッドとグリーン側の勝利となった。
「なかなか良い試合だったね」
「…あぁ」
グリーンのポケモンもレッドのポケモンも、2体中1体は戦闘不能にされてしまった。
「危ないところは多々あったけど…さっきよりはましになったんじゃね?」
「何言ってんの。優勝するんでしょ?」
レッドに言われてグリーンは「それはそうだ」と言って笑う。
しかし…
グリーンは反対側にいる、悔しそうなコトネと完全に打ちひしがれているヒビキを見やった。
なぜだか、コトネの攻め方がいつもより強烈だった気がする。
こちら側のやられた2体も、コトネのポケモンに攻め負けたと言っても過言ではない。
対するヒビキはコトネの方ばかりちらちら窺いながら戦っていた。
あの二人に何かあったのだろうか。
それともタッグバトルをやらせたらああなるだけなのだろうか。
「あの子たち、いいね。まだまだ強くなる」
いつの間にかレッドもグリーンの横に並んであちら側を見ていた。
それに気づいたコトネがブンブンと大きく手を振る。
それにレッドがヒラヒラと手を振り返したため、コトネは何事かを叫んで隣で打ちひしがれるヒビキをバンバンと叩いていた。
「げ、元気だな…」
「ん、可愛いね」
それはあの光景を見て言ったのか、それとも二人のチコリータとヒノアラシの着ぐるみを指して言ったのか、はたまた両方だったのか。
まぁ、そんなことはグリーンからしたらどちらでも良かったのだが。
「タッグバトル…意外と難しいなぁ…」
レッドは小さく溜息をつくと、トイレへと足を踏み入れた。
少し迷ったものの、男子トイレへと入る。
幸いにも周りに人はいなかった。
女子トイレには入り慣れているとはいえ、さすがに男のときに入るのは気が引ける。
実際女装なのだから、誰かに見られても文化祭だからと軽く流せるだろう。
そんなことをぼんやり考えながら用を足して、手を洗い外へ出ようとする。
が、入り口に人が立っているのが見えてレッドはギクリとして足を止めた。
急激に早くなる心臓の鼓動は、見られたことに対してではない。
そのシルエットには見覚えがあった。
そう、忘れようとしても忘れられない、あの…
「駄目じゃないか、女の子が男子トイレなんか入っては…」
「え……ぁ…」
一歩後ずさる。
一歩間を詰められる。
「ど、して…ここ、に…?」
喉が渇いてうまく声が出ない。
近づいてくる男性は張り付いた嘘くさい笑みを浮かべたままこちらに手を伸ばしてくる。
「随分可愛らしい格好をしているね、レッド」
「…っ、サカキ…」
身体が一気に冷えていくのが分かる。
怖い、怖い、怖い…
伸ばされた手を思わず振り払うと、素早く手首を掴まれて引き寄せられた。
身体はガクガクと震え、その顔も血の気を失っている。
そんなレッドを見て、サカキは満足そうに頷いた。
「元気そうで何よりだよ。おまえの噂はよく聞いている」
「っ、やっ!!」
サカキは、手首を掴んだままレッドを引きずってトイレの個室に押し込めた。
抵抗しようにも、恐怖で身体がすくんでしまって力が入らない。
「ど、して、ここが…?」
「レッドが何処にいるかなどとっくに知っていたよ。しばらく泳がせてみたがね。どうやら店ではとても評判が良いようじゃないか」
「…っ!」
レッドは精一杯サカキを睨むが、相手はそれすらも楽しそうに受け止めて笑っている。
更には片手で両手首を掴まれ、頭上で難なく拘束されてしまった。
「レッドも私といっしょで必死のようだ」
「…その、口ぶりだと噂も聞いているんでしょ」
「あぁ、とんだ尻軽女だと、ね」
「今更…そんなの、傷つかない…から」
実際その通りだし、と自嘲気味に呟く。
身体と心の痛みに耐えながら、言われたとおり自分も必死だったのだ。
「しかしまだ見つかっていないようだ」
「…見つかったって、言ったら…?」
そこで初めてサカキは表情に変化を見せた。
しかしまたすぐに元の表情に戻ってレッドの顎をグイと掴むと、その顔をジッと見た。
「嘘だな。呪いは解けていない」
「…まだ、足りないだけ。絶対当たりだから…」
挑発的に見返されて、サカキは今度こそ表情を歪めた。
手首は頭上で拘束したまま、洋式便座の上にレッドを押し倒す。
「いっ…!」
「誰だ?まさか一緒にいた彼か?」
さぁね、と小さく呟けば、グイと空いた方の手で片足を大きく持ち上げられる。
いきなりの行動に息をのんでサカキの方を見れば、一目でやばいと分かる顔つき。
そのまま足を肩に担ぎ上げられて、レッドは小さく悲鳴を上げた。
「や、やめっ…!何する気!?」
「あの電気鼠は何処だ?おまえのことだから肌身離さず持っているんだろう?」
「今日は持ってない…!」
「嘘だな。どこに隠してる?ここか?…それともここか…?」
「ひっ、や…あっ、さ、触るな!!」
浴衣の裾をたくし上げられ、中をまさぐられる。
恐怖といろいろで生理的に涙が溢れてきて、レッドは嫌々と大きく首を振った。
「やだっ、誰か!!誰かーー!!!」
「残念だったな。バリヤードに壁を張らせてあるから誰もここには入ってこれない」
「っ!?」
「あの電気鼠にはドアも壁も全て壊されたからな。全く優秀な相棒だ。あの後修理代がどれだけ高く付いたか…」
「助けて…、誰かっ、グリ、グリーン!!!」
「だから誰も来ないと言っている。聞き分けがないな」
「ひぅっ、こんな、やだぁ!!!」
帯は解かれ、前もはだけられる。
帯の折り目に隠してあったボールがちらりと見えて、サカキはニヤリと笑みを浮かべた。
「そもそもピカチュウはポケモン保護条例で指定されている。持っていては犯罪だぞ」
「おまえが勝手に作った条例だろ!?」
帯を背中に庇いながら叫ぶ。
恐怖と羞恥とが混じり合って涙が止まらない。
「あまり抵抗するようなら無理矢理奪うことになるが…」
「っ、今は、男、だ…!」
「今に限ってはそれは関係ないな」
さぁっと顔から血の気が引く。
便座の上ということと足が担ぎ上げられていることが原因で体勢は非常に不安定である。
「た、助けて!!グリーン!!」
無意識に彼の名を呼ぶ度にサカキが不機嫌になっていくことがレッドには分かっていない。
しかし、サカキが再びレッドに手を伸ばしたとき、トイレに誰かが走り込んできた。
「レッド!?いるのか!?」
「グ、グリー…」
目を見開いたのはサカキもレッドも同じだった。
サカキは小さく舌打ちするとボールを取り出す。
中から出てきたのはフーディンだった。
「レッド、私も一般参加として今回のバトルに出ているぞ。決勝戦で待っている」
「っ!?」
グリーンが個室のドアを開け放つと同時に、フーディンがスプーンを上に掲げた。
瞬間、グリーンの目の前で人影が跡形もなく消える。
「テ、テレポート…?」
唖然としてたグリーンだったが、目の前の光景に気づいた途端、今度は驚愕に目を見開いた。
「レ、レッド、おまえ…」
「どうして、ここが…?」
「や、おまえ帰ってくるの遅いし、俺もトイレ行こうと思って入ろうとしたんだけど何か壁があってトイレに近づけねぇし…」
そこまで聞いたところでレッドは後ろに控えるバンギラスに気づいた。
「かわらわり…覚えてたんだ…」
「っていうか、何があったんだよレッド!?」
グリーンの顔は見ていられないほど真っ赤に染まっている。
そこでレッドはやっと自分の格好に気づいた。
帯は完全に解けてしまっているし、浴衣はもう着ているか着ていないか分からないくらいになってしまっていた。
レッドは呆然としてグリーンを見た。
その頬は涙に濡れてぐしょぐしょだし、喉からはまだ嗚咽が漏れている。
グリーンから見たら完全に強姦現場だ。
「…っ、とにかく警察呼んで…」
「いい」
「は!?」
「何もされてないし、呼んだとしてもどうせ奴の息がかかってるから無駄…」
「ど、どういう意味…」
「それより、グリーン…」
レッドはグイとグリーンの腕を引いた。
涙に濡れてさらに深みを増した深紅がグリーンを捕らえる。
「絶対、優勝するから…。負けられなく、なった」
そう言うレッドの目にグリーンは紅蓮の炎を見た気がした。
→8
散々犯され、泣きわめき叫び絶望する日々。
そんな中で涙ながらにこう尋ねたことがあった。
この問いかけに彼は何と答えたのだったか。
『欲しいんだ、どうしても。継ぐ者が欲しい。片方だけでは…駄目だったんだよ』
よく分からなかった。
今も、よく分からない。
ただ、彼は毎日ボロボロだった。
必死だった。
まるで何かに取り憑かれたように毎日僕のところに来ては、まだ駄目だと言って歯噛みする。
『まだ駄目』の意味は分かる。
それが『やっと叶った』になったとき、自分に何が起きるのかも分かっていた。
だから、早く逃げなきゃって、出口の無い部屋でいつも思っていた。

7
「で、何で浴衣?」
レッドは明らかに険のこもった目つきでグリーンを見た。
「いやぁ、貸してもらえてよかったな!俺の顔の広さが分かるよなぁ~」
「だから、何で浴衣…?」
「や、俺甚平じゃん?おそろいって感じでいいじゃん」
「じゃあ僕も甚平でいいじゃん」
「女物は余ってなかったんだよ」
「じゃあ男物でよかった」
「まぁまぁそんなこと言わずに。ばれたくねーんだろ?」
ニヤニヤとこちらを見てくるグリーンを本気で殴りたい気持ちにおそわれる。
それをグッと堪えてレッドは前で文庫結びにした帯を後ろに回した。
赤地に金色の金魚が踊る上品且つ華やかな浴衣は、どこから借りてきたのかは分からないが後夜祭のために準備されたものらしい。
対してグリーンはタコ焼き屋をやっていた際に着ていた、紺に黒の縦縞が入った甚平のままである。
クラス全員甚平を着ていたようだから、予備がないというのは些か不自然である。
まさか…とグリーンのほうを再びじと目で見るが、グリーンはどこ吹く風でポケモン何にしようかなぁと楽しそうに呟いている。
レッドは釈然としないままウィッグをかぶり、二つに分けた髪を片方ダッカールで留めると、口に咥えていたゴムで器用におだんごを作ってピンで留めていった。
所要時間3分ちょっと。
最後に赤い大輪の牡丹をおだんごの横に留めたところで、グリーンがぽかんとしてこちらを見ているのに気づいた。
「な、何…?」
「レッド手際良すぎじゃね…?」
「…っ」
しまったと慌てて目をそらす。
髪はいつもやってるから、浴衣は店で着たことがあるから、などとは言えるはずがない。
余談だが着物の着付けも自分で出来たりする。
「えっと、昔こういうの手伝わされたことがあって…それで覚えたっていうか…」
「へぇ…」
我ながら苦しいと思うが、それくらいしか咄嗟に思いつかなかったレッドは恐る恐るグリーンを覗った。
が、そこには「すげぇ」と顔を輝かせるグリーンが。
実際、自分のをやるのと人にやるのとでは全然違うので、レッドが鏡も見ずにここまで出来るのは今の理由では成り立たない。
しかしそんなことにとんと縁のないグリーンには十分な理由だったらしい。
「しかしまぁ…似てるよなぁ…」
「…誰に?」
「前にも聞いたじゃん。"紅"っていう子にレッドがすんげぇ似てるんだって。並んだら双子並だぜ絶対」
まじまじと見つめられてレッドは耐えきれずに再び目をそらせた。
絶対親戚…いや姉弟か双子だろとしつこく詰め寄ってくるグリーンの足を思い切り踏みつける。
本日二度目の足への襲撃に、グリーンは悲鳴を上げてレッドへ非難の目を向けてくるが、口をへの字にするレッドにこれ以上問い詰めても無駄だと判断したのか、溜息をついてそばにあったベンチへと腰を下ろした。
影で作業していたレッドも、足履きまで一通り身支度が整うと荷物を挟んでグリーンの隣に座った。
端から見れば美男美女の和服カップルだが、生憎何の催し物もない裏庭には人はほとんどいないためはやし立てる人もいない。
「っていうか、仮装しなきゃバトル参加出来ないって何なの?」
「あぁー…あれだろ、一イベントとして盛り上げたいんだろ」
要するに普段出来ないことを…ということらしい。
前のようにジャージで出ようとしていたレッドにはとても嬉しくないオプションである。
さすがに浴衣に帽子をかぶるわけにはいかないので今回は顔出しということになる。
そのことに不安を感じるものの、エントリーはもう済ませてしまっているため後戻りはできない。というかしたくない。
「…手ぇ抜いたりしたら許さないからね」
「こっちの台詞だよ」
こっちは金券までかかってるんだからな!と偉そうに言うグリーンに思わず口元が緩みそうになるのを耐えて、レッドはグリーンに懐から出したメモ用紙を押しつけた。
不思議そうな顔をするグリーンに、「使用ポケモンとそのポケモンが覚えてる技」と付け足す。
「って、もう選んできたのか!?」
「うん、先に欲しいの捕られちゃったら嫌だし」
先に、と言ってもレンタルポケモンの品揃えはかなり豊富である。
別に先に選んでも後に選んでも変わらない気がする…と思ったグリーンだったが、メモされているポケモンの名前を見て目を見開いた。
リザードン、カメックス、フシギバナ、カビゴン…
「これ、前の時といっしょ…?」
「うん、同じ子選んできた」
「同じ子って…」とグリーンは呆れた顔でレッドを見る。
「そんなんボールの外から見て分かるのかよ」
「分かるよ。ポケモンはみんな違う顔してるからね」
グリーンは今度こそ完全に絶句した。
自分のポケモンと他のポケモンの顔なら何となく違いは分かったものだが、レンタルポケモンの顔まで覚えているなんて…
「せっかくあの子たちのことちょっとだけ分かったから、もっと知りたいなぁって」
「…ん?あとはラプラスとエーフィ……。ピカチュウ使わねぇの?」
前回はそのピカチュウにボロ負けしたグリーンである。
しかしレッドは首をゆるゆると横に振った。
「違うピカチュウなんて使ったら僕のピカチュウが拗ねちゃうから」
腰のあたりのボールがカタカタ小さく動くのを感じて、レッドは内心でごめんねと手を合わせた。
本当は使ってあげたい。
思い切りバトルさせてあげたい。
しかしその最強の相棒は今回ばかりは使ってあげられない。
さすがに外部から人が来るとなれば、ピカチュウだけレベルが明らかに高いことが分かる人が出てくるだろう。
「っていうかダブルバトルになるってこと忘れるなよ…?」
「グリーンが僕に合わせてね。そういうの得意そうじゃん」
「おまえなぁ…!」
それなら一緒にポケモン選ぶぞ!
そう言ってグリーンは立ち上がると会場の方にずんずん歩いて行く。
その後を小走りに追いかけるレッドの目は少しだけ楽しそうだった。
***
タッグバトル。改造されたバトルフロア。そして強制仮装。
これだけの餌があれば観客が飛びつくのも当然で…
「うるせぇえぇえええっっ!!何も聞こえねぇよ!!」
「グリーンもうるさいよ」
「うっせぇ!!」
要するに、会場の観客席は人で埋まっていた。
本気で観客席に隙間が見えない。さすが文化祭。
グリーンは観客の歓声に耳をふさぎつつ、先ほどからポケモンをボールから出して何かしているレッドに近づいた。
ポケモンは会場に入ってからしか出してはいけないことは徹底されている。
レッドは会場に入ってから時間がないとばかりにポケモンを全員外に出していた。
エーフィを除く5匹が巨体のため、端から見れば怪獣に女の子が飲まれようとしているような光景である。
「みんな元気だった?久しぶりだね。また一緒に戦ってね」
よしよしと撫でてやれば巨体軍団が嬉しそうに鳴き声をあげる。
グオォオォオ、とか、ゴォオォオオとか。
グリーンは思わずレッドに近づく足を止めていた。
怖い、怖すぎる。
というか、何故レンタルポケモンがトレーナーにあんなに懐いてるんだ。おかしいだろ。
グリーンの心の叫びなど聞こえるはずもないレッドは一匹ずつに何事かを話しかけてはギュッと抱きしめていく。
そして最後に大人しく座っているエーフィに近づいた。
「エーフィは初めましてだね。よろしく」
レッドはエーフィのその美しい紫色の目をジッと見つめる。
エーフィもレッドを品定めするかのように、その深紅の目をジッと見つめる。
見つめ合うこと十数秒、エーフィはゆっくりと立ち上がるとレッドに向かって恭しくお辞儀をした。
「!?」
グリーンが唖然とするそばで、レッドは嬉しそうにエーフィの前にしゃがみ込み、その紫色の上品な毛並みを撫でた。
エーフィにも何事かを話している。
さすがに内容までは聞き取れなかったが。
グリーンが固まっているうちに、レッドは満足したのか全員をボールに収めてグリーンのほうに歩いてきた。
そこでやっとグリーンはハッと我に返る。
「お、おおおまえいったい何やって…」
「…?ミーティングだよ」
首をかしげてそう答えるレッドは、仕草は可愛らしいものの、その目は完全に闘志でぎらついていた。
そして始まった第一試合。
結果から言えば、一応勝利はしたものの中身はボロボロだった。
「ねーよ!!無理!!おまえのポケモンが技出すタイミング分かんねーもん!!」
「ポケモン見てれば分かるでしょ」
「分かんねーよ!っていうか4匹も目がいかないし!」
レッドは呆れたような顔でこちらを見てくる。
グリーンはグッと歯噛みすると、次の瞬間「あ"ー!」と叫んで頭をガリガリかいた。
レッドは前回と同様、ポケモンに技の指示を出していなかった。
だから、なんというか、要するに、タイミングどころか何の技を出すのかもグリーンには分からない。
「おまえどうやって指示出してんの?さっぱり分かんねーんだけど」
これは前回のバトル後も聞きたかった質問である。
隣で見せつけられて、改めて隣に立つ浴衣の少年の凄さを知った。
「指示…ね。僕は技を出すタイミングを合図するだけ。技の指示はしてないよ」
「はぁ!?」
「何を出せば良いのかはポケモン自身が一番分かってる。迷ったときはこっちを見てくるから、指で1から4を示してあげるだけ。さすがにアイコンタクトじゃつきあいの短いポケモンだと分からないから」
いや、それでも十分化け物級だという言葉をグリーンはグッと飲み込んで、その1から4の順番はどう決めているか問う。
あいうえお順かと想像していたグリーンだったが、レッドから返ってきたのは「得意な技順」という答えだった。
「だからどーやって!?」
「だから直接聞いただけだよ」
レッドはグリーンの剣幕に押されつつぼそぼそと答える。
グリーンは今度こそ頭を抱えてしまった。
レンタルポケモンとどうしてそこまで意思疎通出来るのかが分からない。
「ホントは声で指示してあげたいけどね。女の格好で男の声はまずいでしょ…」
レッドは恨めしそうに襟元の集音マイクを指さした。
前回もそうだったが、ここのバトルではトレーナーの声が観客席にも聞こえるようにマイクの装着が義務づけられている。
下手に喋れば会場全体に自分の声が響き渡ることになるのである。
「裏声で頑張れよ。レッドそこまで声低くないからいけるって」
「…無茶言わないでよ」
静かに睨み付けられ、グリーンも黙って口を閉じる。
レッドはグリーンに先ほど渡したメモの技名に、それぞれ1,2,3,4を書き込んで、それをぶっきらぼうにグリーンの胸へと押しつけた。
「…分からないなら覚えて。それくらい楽勝でしょ?指の合図は次から毎回やるから」
「…文武両道の俺様をなめんなよ?」
グリーンはもらった紙を十数秒ながめるとそれをくしゃりと丸めた。
「でも、僕のほうばっかりじゃなくてちゃんとポケモンを見ててね。ジッと見てれば、だんだん分かってくるよ」
「…じゃあ、俺も次同じポケモン使ってみようかな」
「…?」
「レッドが前回の数回の試合で今のポケモンとの関係を築いたなら、俺もちょっと真似してみたいって思った。それだけ」
そう言うと、レッドは別にいいんじゃない?と小さく笑った。
その顔が可愛すぎて動悸がしたことは絶対にレッドには内緒である。
そして二試合目は、運が良いのか悪いのか、ヒビキとコトネが対戦相手となった。
「ヒッ、ヒビキくん見てぇぇえぇええええっ!!グリーンさんの隣にいる人!!前回の定期バトルの優勝者!!!!」
「え?そうなの?」
ヒビキが目を凝らしてグリーンの隣に立つ女子を見る。
ヒビキもコトネと同様前回戦ってボロ負けしたのだが、前回はジャージでしかも帽子をかぶっていたため、顔がよく分からなかった。
遠目で分かったコトネに感心しつつ、同時に再びあの時の焦りが蘇る。
「コトネ、分かってるよね…?バトルにちゃんと集中し…」
「はぁあぁぁあああっ、すっごい綺麗…/////グリーン先輩知り合いだったんだ…!っていうか和服お揃い!?まさか彼女!?羨ましい…!あとで紹介してもらおっ!!」
今にもぴょんぴょん飛び跳ねそうな勢いのコトネを、ヒビキは呆然と見ていた。
これは駄目だ。いろんな意味で駄目だ。
冷や汗が背中を伝っていく。
「コ、コトネ!」
ヒビキはコトネの肩をガッと掴むと、無理矢理自分の方へ向かせた。
いきなりのことにコトネはきょとんとしてヒビキの方を見る。
「こ、これはタッグバトルでっ、二人が協力しなきゃ駄目で…!だからコトネは、ちゃんと僕のほうを見てて!!」
「ヒビキくん…」
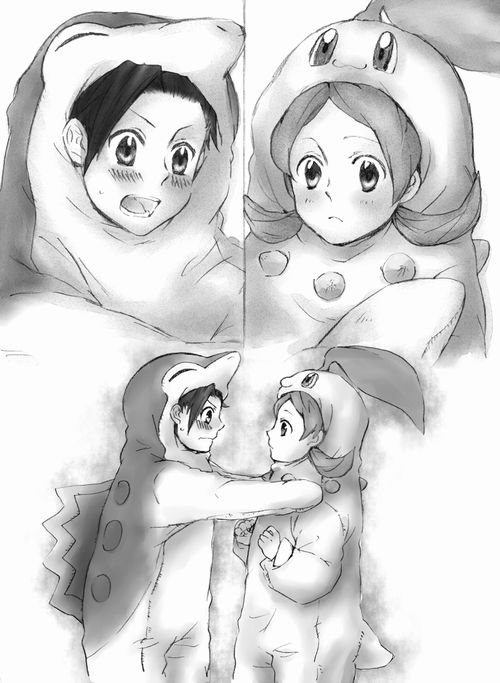
コトネはしばらく赤く染まったヒビキの顔を見ていたが、不意ににっこり笑った。
「当然だよ!絶対勝とうね!二人ともフルボッコにしちゃおう!ほら、やっぱり、残念だったねって言って不敵に微笑んでくるのもいいんだけど、負かせて打ちひしがれた表情はもっと見たいっていうか、打ちのめされるのもいいんだけど、それ以上にあの人を打ちのめしたいっていうかーーーー!!!!!」
頬を上気させて捲し立てるコトネに、ヒビキは目の前が真っ暗になった。
***
白熱したバトルの末、結果は4対2でレッドとグリーン側の勝利となった。
「なかなか良い試合だったね」
「…あぁ」
グリーンのポケモンもレッドのポケモンも、2体中1体は戦闘不能にされてしまった。
「危ないところは多々あったけど…さっきよりはましになったんじゃね?」
「何言ってんの。優勝するんでしょ?」
レッドに言われてグリーンは「それはそうだ」と言って笑う。
しかし…
グリーンは反対側にいる、悔しそうなコトネと完全に打ちひしがれているヒビキを見やった。
なぜだか、コトネの攻め方がいつもより強烈だった気がする。
こちら側のやられた2体も、コトネのポケモンに攻め負けたと言っても過言ではない。
対するヒビキはコトネの方ばかりちらちら窺いながら戦っていた。
あの二人に何かあったのだろうか。
それともタッグバトルをやらせたらああなるだけなのだろうか。
「あの子たち、いいね。まだまだ強くなる」
いつの間にかレッドもグリーンの横に並んであちら側を見ていた。
それに気づいたコトネがブンブンと大きく手を振る。
それにレッドがヒラヒラと手を振り返したため、コトネは何事かを叫んで隣で打ちひしがれるヒビキをバンバンと叩いていた。
「げ、元気だな…」
「ん、可愛いね」
それはあの光景を見て言ったのか、それとも二人のチコリータとヒノアラシの着ぐるみを指して言ったのか、はたまた両方だったのか。
まぁ、そんなことはグリーンからしたらどちらでも良かったのだが。
「タッグバトル…意外と難しいなぁ…」
レッドは小さく溜息をつくと、トイレへと足を踏み入れた。
少し迷ったものの、男子トイレへと入る。
幸いにも周りに人はいなかった。
女子トイレには入り慣れているとはいえ、さすがに男のときに入るのは気が引ける。
実際女装なのだから、誰かに見られても文化祭だからと軽く流せるだろう。
そんなことをぼんやり考えながら用を足して、手を洗い外へ出ようとする。
が、入り口に人が立っているのが見えてレッドはギクリとして足を止めた。
急激に早くなる心臓の鼓動は、見られたことに対してではない。
そのシルエットには見覚えがあった。
そう、忘れようとしても忘れられない、あの…
「駄目じゃないか、女の子が男子トイレなんか入っては…」
「え……ぁ…」
一歩後ずさる。
一歩間を詰められる。
「ど、して…ここ、に…?」
喉が渇いてうまく声が出ない。
近づいてくる男性は張り付いた嘘くさい笑みを浮かべたままこちらに手を伸ばしてくる。
「随分可愛らしい格好をしているね、レッド」
「…っ、サカキ…」
身体が一気に冷えていくのが分かる。
怖い、怖い、怖い…
伸ばされた手を思わず振り払うと、素早く手首を掴まれて引き寄せられた。
身体はガクガクと震え、その顔も血の気を失っている。
そんなレッドを見て、サカキは満足そうに頷いた。
「元気そうで何よりだよ。おまえの噂はよく聞いている」
「っ、やっ!!」
サカキは、手首を掴んだままレッドを引きずってトイレの個室に押し込めた。
抵抗しようにも、恐怖で身体がすくんでしまって力が入らない。
「ど、して、ここが…?」
「レッドが何処にいるかなどとっくに知っていたよ。しばらく泳がせてみたがね。どうやら店ではとても評判が良いようじゃないか」
「…っ!」
レッドは精一杯サカキを睨むが、相手はそれすらも楽しそうに受け止めて笑っている。
更には片手で両手首を掴まれ、頭上で難なく拘束されてしまった。
「レッドも私といっしょで必死のようだ」
「…その、口ぶりだと噂も聞いているんでしょ」
「あぁ、とんだ尻軽女だと、ね」
「今更…そんなの、傷つかない…から」
実際その通りだし、と自嘲気味に呟く。
身体と心の痛みに耐えながら、言われたとおり自分も必死だったのだ。
「しかしまだ見つかっていないようだ」
「…見つかったって、言ったら…?」
そこで初めてサカキは表情に変化を見せた。
しかしまたすぐに元の表情に戻ってレッドの顎をグイと掴むと、その顔をジッと見た。
「嘘だな。呪いは解けていない」
「…まだ、足りないだけ。絶対当たりだから…」
挑発的に見返されて、サカキは今度こそ表情を歪めた。
手首は頭上で拘束したまま、洋式便座の上にレッドを押し倒す。
「いっ…!」
「誰だ?まさか一緒にいた彼か?」
さぁね、と小さく呟けば、グイと空いた方の手で片足を大きく持ち上げられる。
いきなりの行動に息をのんでサカキの方を見れば、一目でやばいと分かる顔つき。
そのまま足を肩に担ぎ上げられて、レッドは小さく悲鳴を上げた。
「や、やめっ…!何する気!?」
「あの電気鼠は何処だ?おまえのことだから肌身離さず持っているんだろう?」
「今日は持ってない…!」
「嘘だな。どこに隠してる?ここか?…それともここか…?」
「ひっ、や…あっ、さ、触るな!!」
浴衣の裾をたくし上げられ、中をまさぐられる。
恐怖といろいろで生理的に涙が溢れてきて、レッドは嫌々と大きく首を振った。
「やだっ、誰か!!誰かーー!!!」
「残念だったな。バリヤードに壁を張らせてあるから誰もここには入ってこれない」
「っ!?」
「あの電気鼠にはドアも壁も全て壊されたからな。全く優秀な相棒だ。あの後修理代がどれだけ高く付いたか…」
「助けて…、誰かっ、グリ、グリーン!!!」
「だから誰も来ないと言っている。聞き分けがないな」
「ひぅっ、こんな、やだぁ!!!」
帯は解かれ、前もはだけられる。
帯の折り目に隠してあったボールがちらりと見えて、サカキはニヤリと笑みを浮かべた。
「そもそもピカチュウはポケモン保護条例で指定されている。持っていては犯罪だぞ」
「おまえが勝手に作った条例だろ!?」
帯を背中に庇いながら叫ぶ。
恐怖と羞恥とが混じり合って涙が止まらない。
「あまり抵抗するようなら無理矢理奪うことになるが…」
「っ、今は、男、だ…!」
「今に限ってはそれは関係ないな」
さぁっと顔から血の気が引く。
便座の上ということと足が担ぎ上げられていることが原因で体勢は非常に不安定である。
「た、助けて!!グリーン!!」
無意識に彼の名を呼ぶ度にサカキが不機嫌になっていくことがレッドには分かっていない。
しかし、サカキが再びレッドに手を伸ばしたとき、トイレに誰かが走り込んできた。
「レッド!?いるのか!?」
「グ、グリー…」
目を見開いたのはサカキもレッドも同じだった。
サカキは小さく舌打ちするとボールを取り出す。
中から出てきたのはフーディンだった。
「レッド、私も一般参加として今回のバトルに出ているぞ。決勝戦で待っている」
「っ!?」
グリーンが個室のドアを開け放つと同時に、フーディンがスプーンを上に掲げた。
瞬間、グリーンの目の前で人影が跡形もなく消える。
「テ、テレポート…?」
唖然としてたグリーンだったが、目の前の光景に気づいた途端、今度は驚愕に目を見開いた。
「レ、レッド、おまえ…」
「どうして、ここが…?」
「や、おまえ帰ってくるの遅いし、俺もトイレ行こうと思って入ろうとしたんだけど何か壁があってトイレに近づけねぇし…」
そこまで聞いたところでレッドは後ろに控えるバンギラスに気づいた。
「かわらわり…覚えてたんだ…」
「っていうか、何があったんだよレッド!?」
グリーンの顔は見ていられないほど真っ赤に染まっている。
そこでレッドはやっと自分の格好に気づいた。
帯は完全に解けてしまっているし、浴衣はもう着ているか着ていないか分からないくらいになってしまっていた。
レッドは呆然としてグリーンを見た。
その頬は涙に濡れてぐしょぐしょだし、喉からはまだ嗚咽が漏れている。
グリーンから見たら完全に強姦現場だ。
「…っ、とにかく警察呼んで…」
「いい」
「は!?」
「何もされてないし、呼んだとしてもどうせ奴の息がかかってるから無駄…」
「ど、どういう意味…」
「それより、グリーン…」
レッドはグイとグリーンの腕を引いた。
涙に濡れてさらに深みを増した深紅がグリーンを捕らえる。
「絶対、優勝するから…。負けられなく、なった」
そう言うレッドの目にグリーンは紅蓮の炎を見た気がした。
→8